お酒を販売するときには、税務署で「酒類販売免許」を取得する必要があります。酒類販売免許には14種類あります。種類により、手続きも異なります。行政書士が対応可能な申請です。今回は、輸出や輸入する場合の免許申請について解説していきます。当事務所では関西圏(大阪・神戸)を中心に対応可能です。
概要
酒類販売免許は酒税法に基づき、税務署長が交付しています。
お酒の販売・代理・媒介をしたい場合は、販売場ごとに販売場の所在地の所管税務署に申請が必要です。
お酒とは、アルコール1%以上のものと定義しています。アルコール消毒液も対象となる場合があります。
お酒の担当者(酒税指導官)は、住所地の管轄税務署に常駐していない場合が多いです。ご相談の際は、事前に税務署にご確認ください。
免許の種類
酒類小売業免許
・一般酒類小売業免許
・通信販売酒類小売業免許
・特殊酒類小売業免許
・期限付酒類小売業免許
酒類卸売業免許
・ビール卸売業免許
・全酒類卸売業免許
・洋酒卸売業免許
・輸出入酒類卸売業免許
・店頭販売酒類卸売業免許
・協同組合間酒類卸売業免許
・自己商標酒類卸売業免許
・特殊酒類卸売業免許
その他酒類卸売業免許
・酒類販売代理業免許
・酒類販売媒介業免許
免許によっては、お酒販売の実務経験が必要な場合があります。
免許取得までの日数
税務署への申請から2ヶ月ほどで結果が出ます。
当事務所でご依頼された場合は、3ヶ月ほどです。
- お問い合わせ(お客様)
- 以下のリンクの入力フォームからご送信ください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFPIvBBUssXPRo3F22ynX3q-_z9LGjSKdukg5Mn0v3yCpy6g/viewform?usp=sf_link
- 税務署との事前相談(行政書士)
- 要件の確認などを行い、スムーズに申請が行えるよう調整します。
- ご依頼(お客様)
- 契約書を交わし、着手金をお支払いいただきます。
- 申請書類の作成・収集(行政書士)
- 申請書類を作成します。
一部、お客様のご協力が不可欠です。
- 免許申請(行政書士)
- 販売場所管の税務署へ申請します。
- 審査(税務署)
- 酒類指導官が在籍の税務署へ移送され、審査されます。
- 結果の連絡(行政書士)
- 税務署より連絡が来ましたら、速やかにお客様へご連絡します。
手数料の残金をお支払いください。
- 免許交付(お客様と行政書士)
- 税務署で登録免許税を納付し、免許の交付を受けます。
免許は再発行されませんので、保管にご注意ください。
免許が受けられないものの一例
- 申請前2年以内に国税 or 地方税の滞納処分を受けたもの
- 正当な理由がなく、不適当な場所に設けようとするもの
- 破産者で復権を得ていないもの
- 飲食店と同一の場所で設けようとするもの
飲食店でお酒の販売は極めて厳しいです。
手数料
(輸 出)12万円+消費税
(輸 入)14万円+消費税
(輸出入)15万円+消費税
※別途、登録免許税9万円
令和2年度の全国の行政書士の報酬額調査では、酒類販売業免許申請の相場は15万円でした。
遠方の地域は、別途交通費や日当を頂戴する場合がございます。
申請書類
申請書
① 販売場の敷地の状況
② 建物等の配置図
③ 事業の概要
④ 収支の見込み
⑤ 所要資金の額及び調達方法
⑥ 「酒類の販売管理の方法」に関する取り組み計画書
添付書類
・ 取引承諾書 or 契約書
・ 土地及び建物の登記事項証明書
・ 酒類販売業免許申請書チェック表
・ 残高証明書等
(販売場が自己所有の建物・土地でない場合)
・ 建物賃貸借契約書
・ 使用承諾書
(法人の場合)
・ 登記事項証明書
・ 定款
・ 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
・ 都道府県&市区町村の納税証明書
(役員がいる場合)
・ 役員全員の履歴書
・ 酒類販売業免許の免許要件誓約書
登記事項証明書と定款の事業目的に「酒類の販売」の記載が必要です。記載がない場合は、目的の変更登記と定款の再作成が必要です。
取引先の取り扱いしているお酒が限られている場合は、その種目のお酒しか輸出入することができません。追加する場合は別途、緩和条件の申出という手続きが必要です。
新規法人でも取得可能です。
輸出入酒類卸売業免許のポイント
実務経験
貿易事務に精通していること
お酒に限らず、アパレルでも精密機器でも良い。
もし、実務経験がない場合は、とりあえず何かを輸出や輸入し、実績を作りましょう。
取引承諾
輸入の場合は、仕入先との取引承諾書が必要です。
輸出の場合は、販売先との取引承諾書が必要です。
契約書がある場合は、契約書が必要です。
取引承諾書は簡単なもので結構です。
所管
財務省 国税庁 都道府県税務局 所管税務署
酒税やお酒の免許についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)
関西圏は、
酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について|国税庁 (nta.go.jp)
最後に
海外で日本食を提供するお店が増えてきています。それに伴い、日本酒(清酒)の需要が見込まれます。また、ジャパニーズウィスキーを資産として保有している層もいます。
例えば、サントリーの山崎などのウィスキーは、買った時点から価値が上がっていきます。
申請にお困りのかたは、いつでもご連絡ください。
大阪市の本町で補助金・起業支援・遺言・相続・家族信託を中心に活動する行政書士
クロスターミナル行政書士事務所:下井
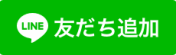

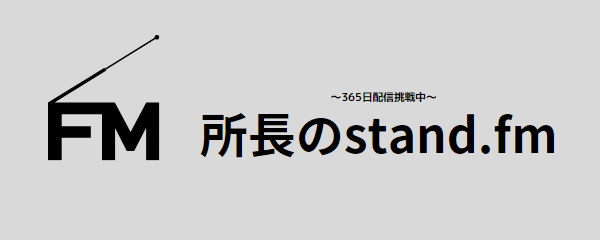
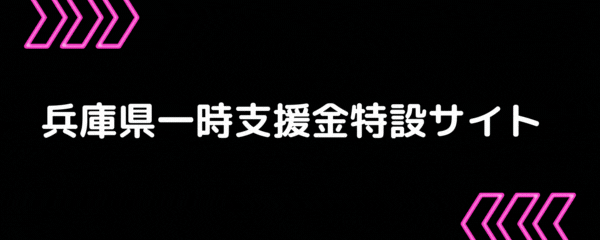
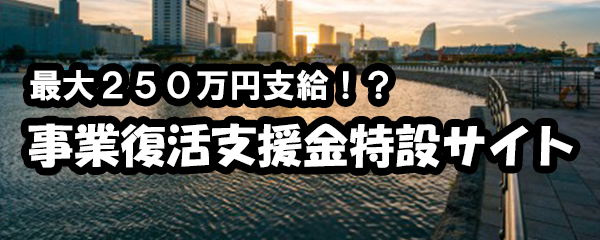



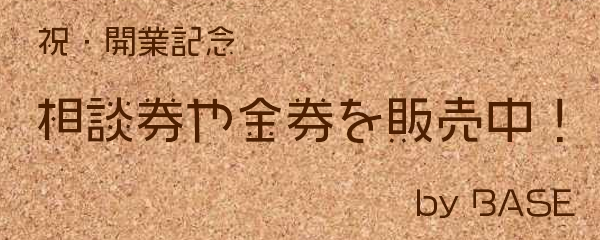
コメントを残す